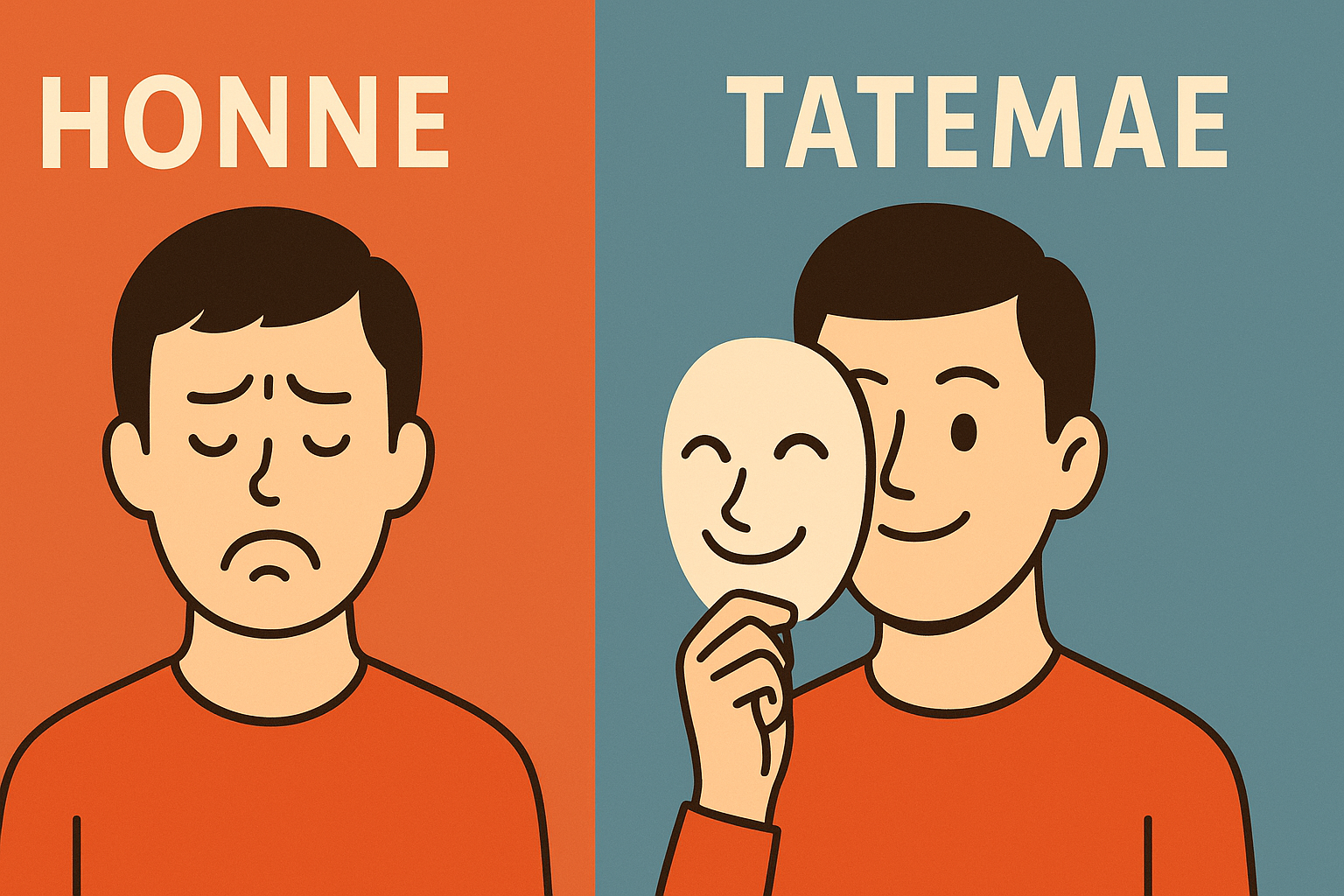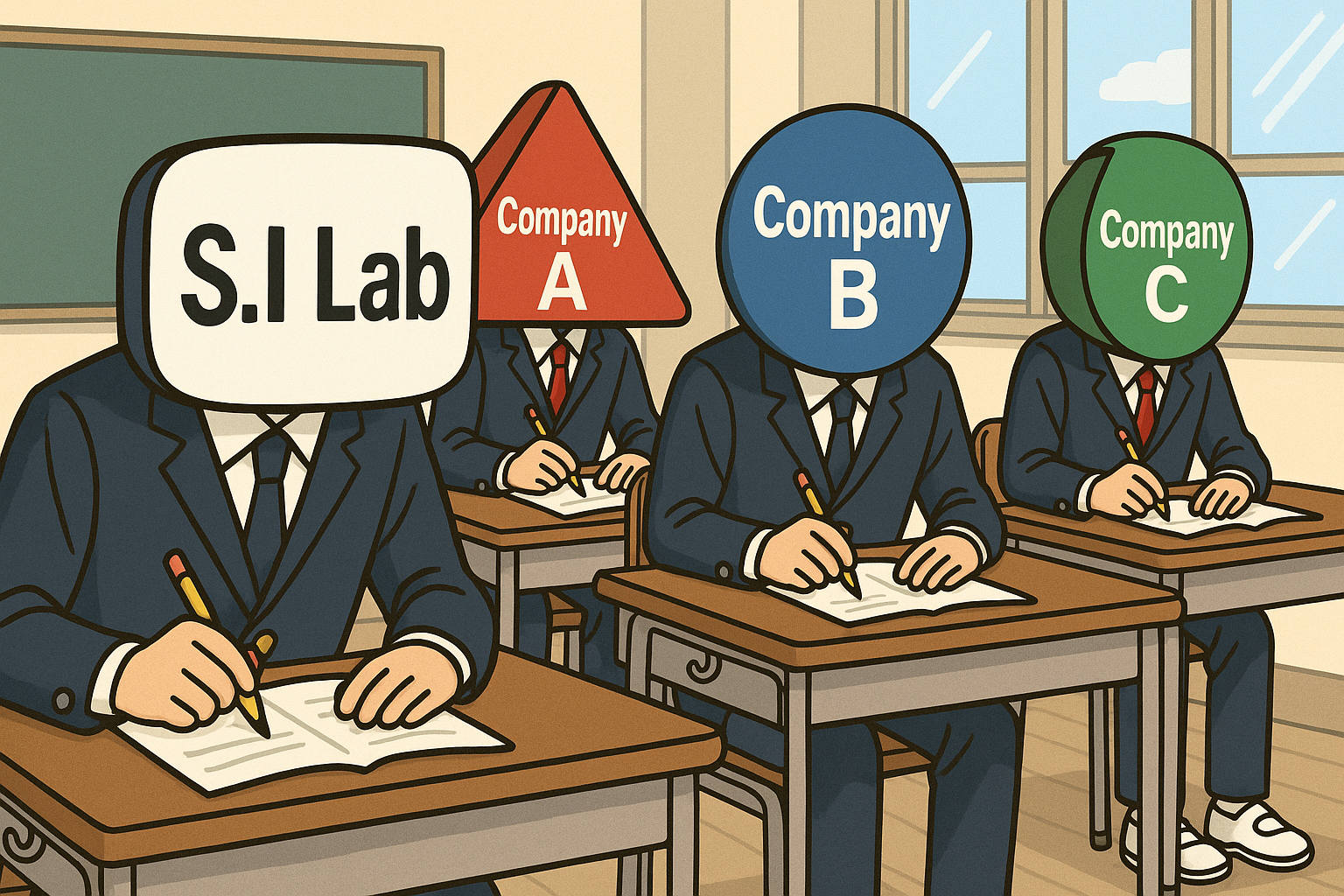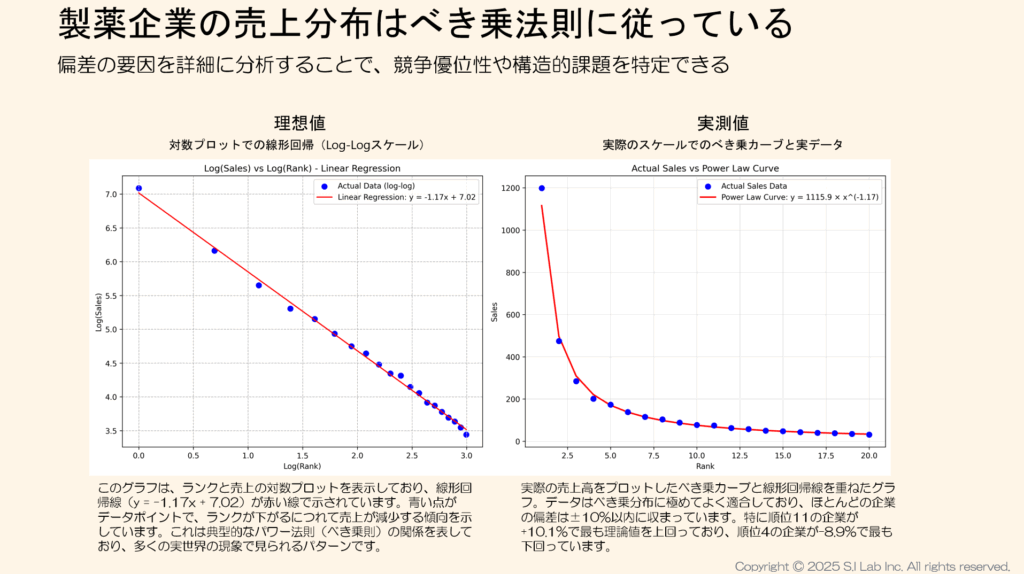CXもペルソナも“幻想”みんな幻想
■ マーケティングとは「価値提供」なのか?
マーケティングの定義を「顧客への価値提供」だとする声は多くあります。
一方で、「それだけでは不十分だ。感謝されてこそ本物の価値提供であり、マーケティングだ」と主張する人もいます。
けれど、私たちは日々の購買行動の一つひとつに本当に価値を感じているでしょうか?
ましてや、「ありがとう」と感謝している場面など、どれだけあるでしょう?
■ マーケティングの定義の幅
1. 「顧客への価値提供」説
フィリップ・コトラーの有名な定義に代表されるように、
「顧客のニーズを満たす価値を創造・伝達・提供する活動」
というのがマーケティングの基本的な定義とされています。
2. 「感謝されてこそマーケティング」説
提供者側の“これは良いものだ”という独りよがりではなく、
受け手である顧客が“ありがたい”と心から思ったときにこそ、本当の価値が届けられたという考え方です。
つまり、感情的な満足まで含めて初めて成立するマーケティングだという立場です。
■ でも、私たちは本当に感謝して買っているのか?
ここにマーケティングの定義の曖昧さが垣間見えます。
- コンビニでペットボトルを買う
- ECサイトで日用品を定期購入する
- 毎月同じシャンプーを買い足す
こうしたルーティン消費に、はたして「価値」や「感謝」はあるでしょうか?
正直なところ、ほとんどの購買は無感情に近いものです。
せいぜい、「面倒だからこれでいいや」という程度でしょう。
■ 感謝は「常に」必要なのか?
結論から言えば、
「感謝されるマーケティング」は理想ではあっても、定義上は必須ではない。
- 価値提供はマーケティングの出発点であり、
- 感謝されることは、その提供価値が“予想を超えた”ときに偶発的に起こる副次的な成果です。
■ 注目すべきは「無感情な購買」の積み重ね
むしろ現実のマーケティングにおいて重要なのは、
「感謝を引き出すこと」よりも、「選ばれ続ける当たり前の存在になること」です。
企業が目指すべきなのは、感動よりも「習慣化」。
価値を“感じさせる”より、疑いなく選ばせる構造をつくることの方が、よほど実務的なマーケティングなのかもしれません。
■ 感謝されるマーケティングが力を発揮する領域
もちろん、感謝される体験をつくることは、ブランド構築や顧客ロイヤルティの観点で重要な差別化要素です。
特に以下のような領域では、その意義が大きくなります。
- 高価格帯の商品・サービス
- BtoBの長期的な契約取引
- 医療や教育といった人生に影響する意思決定が含まれる分野
ただし、それはマーケティング全体に普遍的に求められる要素ではありません。
■ そもそも「価値」とは何か? その曖昧さ
マーケティングでは「価値を提供する」と簡単に語られますが、そもそも「価値」とは何を指すのでしょうか?
1. 主観的価値
顧客が「良い」と感じれば、それが価値だという考え方。
しかし、
- 同じ商品でも人によって価値の感じ方は異なり、
- 同じ人でも、時間や状況によって価値は変化します。
例:砂漠での「水」と、都会のコンビニでの「水」は、同じ商品でも価値がまったく異なる。
2. 市場価格=価値?
価格は一見、価値の客観的な指標のように思えますが――
- ブランド力、情報格差、販売環境によって大きく変動します。
- 同じペットボトルでも、空港とスーパーでは価格も価値も違います。
3. 顧客の反応=価値の証明?
「売れた」ことが価値の証明かのように言われますが、それはマーケティングの効果、
つまり、「情報操作」や「印象形成」に過ぎない場合も多く、
本当に満足されたかどうかはわかりません。
■ 「価値提供」は自己満足で終わることもある
マーケターや企業が「これは価値がある」と信じていても、
- 顧客に届かなければ無価値
- 顧客が使ってガッカリすれば逆効果
提供した“つもり”と、受け取られた“現実”には深いギャップがあります。
■ では、マーケティングは何を軸にすべきか?
このように、「価値」や「感謝」が曖昧な時代において、マーケティングを再定義するなら、
「選ばれる理由をつくること」
あるいは
「行動を引き出す仕掛けを設計すること」
――この2つが、より本質に近い答えではないでしょうか。
外発的動機から「自分で選んだ」と思わせるような、内発的動機づけへと導く、
行動科学・実証ベースのマーケティングが、今後ますます求められるのです。
■ CXもCUも、すべては“仮定”の上に立っている
そう考えると、マーケティングの主流とされている以下のフレームワークも、
すべて“幻想”ではないか?と疑いたくなります。
● CX(Customer Experience:顧客体験)
→ 顧客接点すべてにおけるポジティブな体験を設計するという概念。
しかし本当に、顧客はその体験を一貫して記憶・評価しているのでしょうか?
● CU(Customer Understanding:顧客理解)
→ 顧客のニーズや心理、行動を理解することがマーケティング成功の鍵とされる。
ですが、顧客自身が自分のニーズに気づいていないことも多い。
「インサイト」と呼ばれるものの多くが、解釈の後付けになってはいないでしょうか?
● ペルソナ
→ 仮想の典型的顧客像をつくって施策を練る手法。
ただしそれは多くの場合、
- 理想化されたモデルにすぎず、
- 社内共有の方便となって実際の顧客と乖離し、
- 仮想の誰かに向けて自己満足の施策が打たれることになります。
● カスタマージャーニー
→ 顧客の思考・行動プロセスを可視化して最適化する手法。
しかし現実の顧客行動は直線的でもなければ、計画的でもありません。
- 突然購入をやめる
- 途中で飛ばす
- 思いつきで行動する
つまり、「モデルとしては便利だが、現実とは異なる」のです。
■ 本質的な問い:「誰のための“理解”なのか?」
これらのフレームは、顧客視点を装いつつも、実際には
企業が“売るために顧客を理解したつもりになる”ための道具
にすぎません。
■ 曖昧な“主観の体系化”の限界
- 顧客理解は仮定や解釈に過ぎず、
- 体験価値は感情的・一時的・変動的、
- ペルソナやジャーニーは抽象化された方便。
それらがあたかも「実在するもの」としてマーケティングに転化される――
これこそが、最大のリスクです。
■ それでも使う意味があるとすれば…
- チーム内での共通言語として
- 仮説立案のための思考の出発点として
ただし、過信すれば現実と乖離するというリスクを忘れてはいけません。
■ まとめ:マーケティングとは誰かの“方便”である
マーケティングとは、顧客理解や体験設計の“正しさ”を競うものではありません。
それらはあくまで仮説であり、現実を動かすための“道具”にすぎない。
変化が激しく予測不能だからこそ、現実を直視し、幻想を鵜呑みにせず、仮説を検証し続けること。
それこそが、今のマーケティングに最も必要な姿勢と言えます。