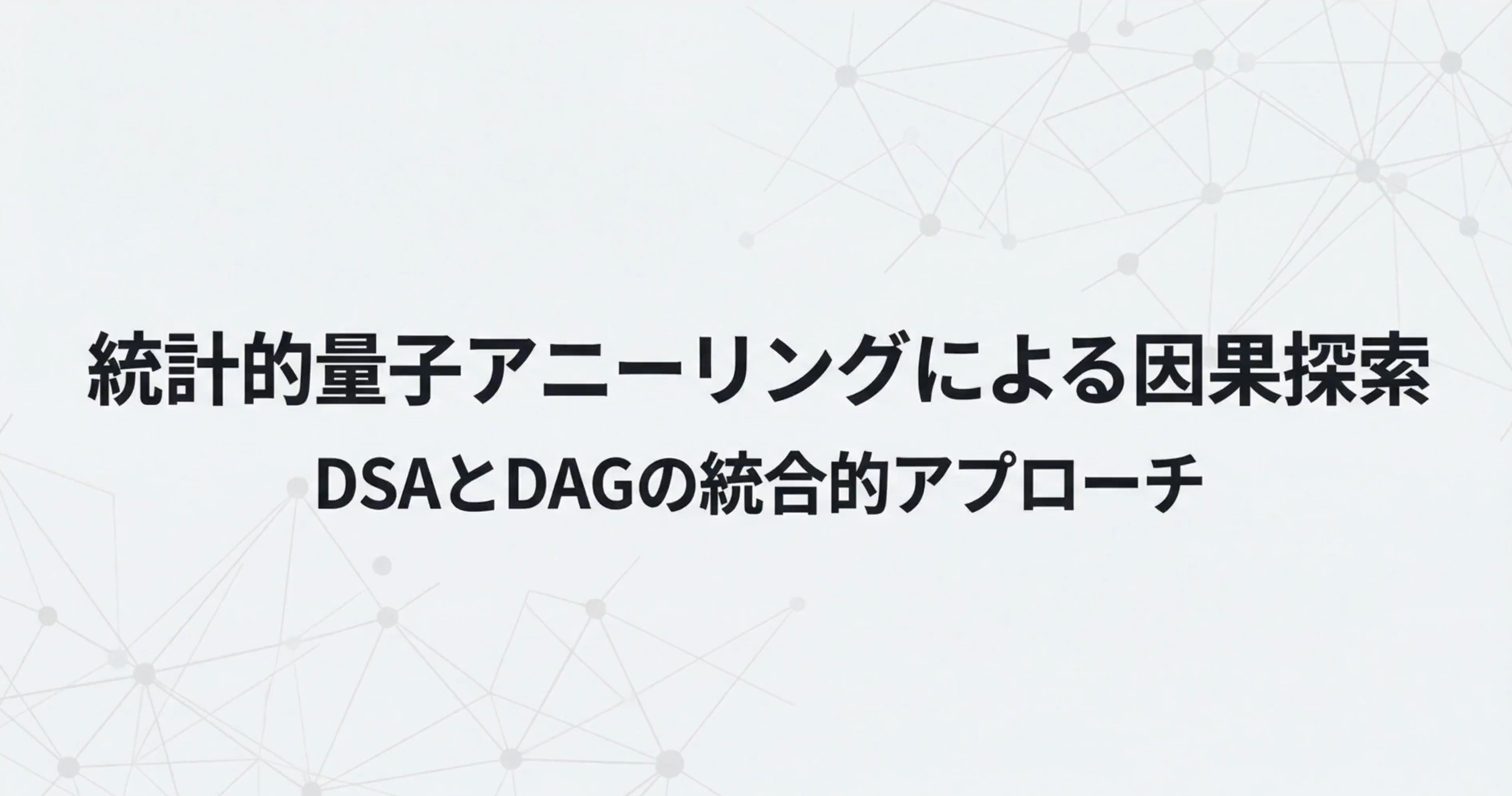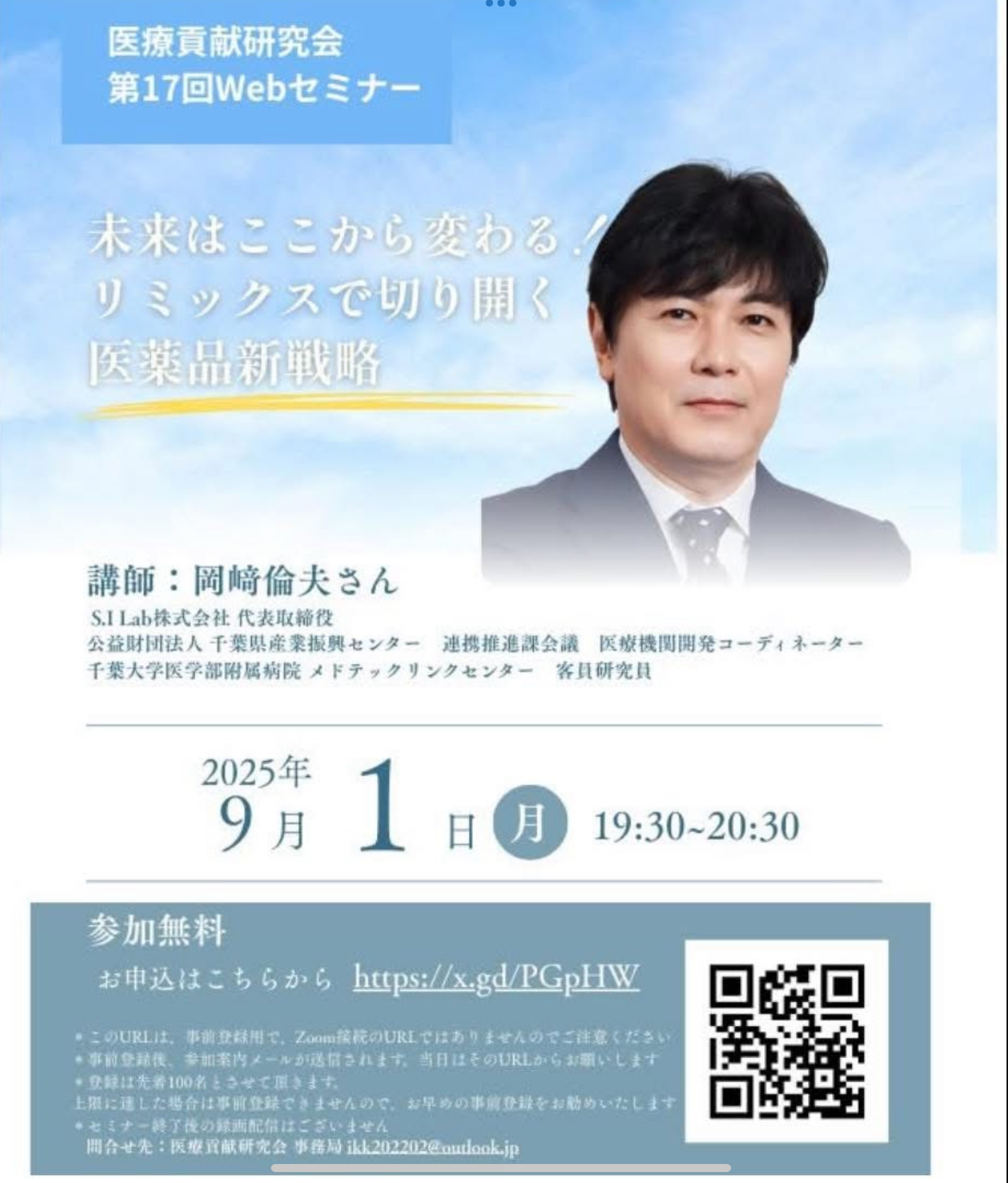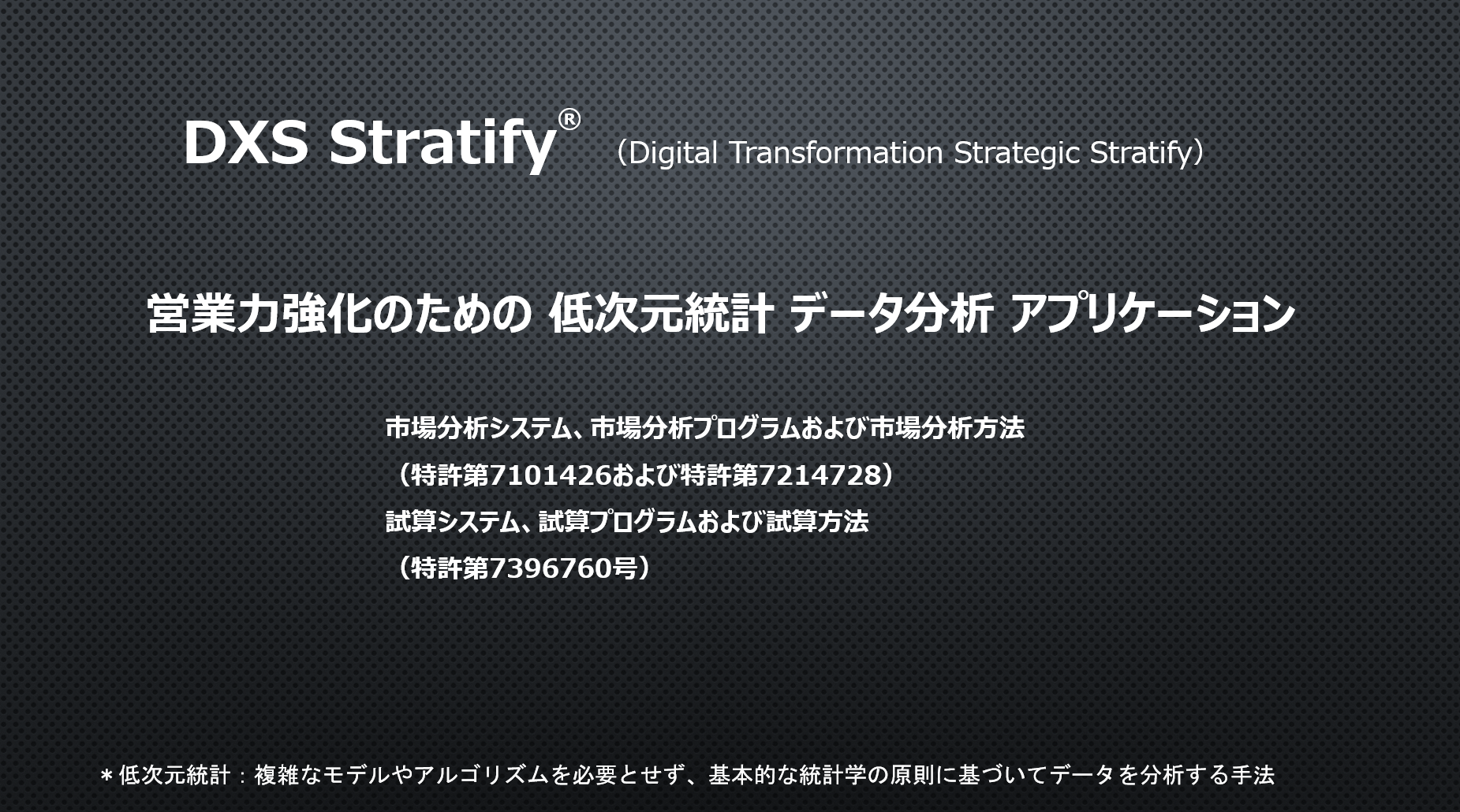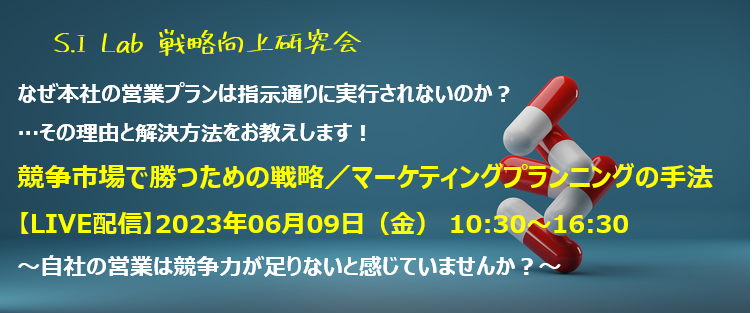だから私はDXS Stratify®を使う
【MRの立場】
なぜ、私はDXS Stratify®を使うのか?
限られた時間、訪問制限、強力な競合…。すべてをカバーするのは不可能で、私は「どこに力を注ぐべきか」で悩み続けてきました。
これまでは経験値や感覚の範囲で判断するしかなく、限界を感じていたのです。
DXS Stratify®は、“売上”ではなく“勝ち負け”でエリアを可視化してくれます。
売れていても競合に押されていれば“守る対象”、競合がいなければ“攻めるべきチャンス”とわかります。
この判断基準により、感覚ではなく数値根拠で訪問優先度を決められるようになりました。
説明責任にも耐えられる行動計画が組めるようになり、社内の評価軸にも合致します。
現場での迷いが減り、行動が確信へと変わりました。
だから私は、DXS Stratify®を使います。行動に迷わず、成果に近づくために。
【営業マネージャーの立場】
なぜ、私はDXS Stratify®を導入するのか?
「数字が悪いなら訪問数を増やせ」——かつてはそれしか言えませんでしたが、正しいとは限らない。
複数のMRを抱える中で、どこにリソースを配分すればチーム全体への寄与率が高まるのか、漠然としていました。
DXS Stratify®は、市場規模・シェア・競合差から“戦うべき場所”を明確にしてくれます。
感覚ではなく数値で、活動効果の濃淡を判断できるようになりました。
戦略マップを通じてメンバーと同じ視点を共有できるようになり、指導に納得感が生まれました。
誰がどこで苦戦していて、どこが伸びしろなのかが一目でわかります。
現場との対話も前向きになり、全体の動きが戦略的に揃い始めています。
だから私は、DXS Stratify®を導入します。勝てるチームをつくるために。
【マーケティング部門の立場】
なぜ、私たちはDXS Stratify®を使うのか?
私たちは戦略立案のために多くのデータを扱いますが、“競合との関係性”は常に見えづらかった。
売上が伸びていても、それが競合優位によるものなのか判断できず、戦略が曖昧になりがちでした。
最適解として示したプランであっても、「もっとこうすべき」「他の方が良いのでは」と納得を得ることが難しい現実があります。
DXS Stratify®は、市場規模・自社シェア・競合ギャップを視覚化してくれます。
ポジショニングやセグメント戦略に直結し、データが具体的な戦略に変わります。
営業やマネージャーと同じマップを見て話せるようになり、部門連携が強化されました。
自分たちの描く戦略が、現場の武器になる感覚が生まれました。
だから私たちは、DXS Stratify®を使います。戦略を、現場で武器に変えるために。
【研修部門・人材開発の立場】
なぜ、私たちはDXS Stratify®を活用するのか?
「戦略的に動け」と言われても、理論や汎用フレームでは現場に響きませんでした。
標準化されたインプットは提供できても、個々のMRの環境に応じた対応までは難しかったのです。
DXS Stratify®は、自社の実データを使って戦略思考を体感できる仕組みです。
受講者は自分の施設を分析し、“どこを守り、どこを攻めるか”を明確に考えるようになります。
戦略=実務として捉えることができ、腹落ちする学びに変わりました。
さらに、思考力・判断力・行動力を一体で鍛えることができます。
研修の場から成果報告までの好循環が、少しずつ生まれてきています。
だから私たちは、DXS Stratify®を使います。「考える人材」を育てるために。
【デジタル推進部門・DX担当の立場】
なぜ、私たちはDXS Stratify®を選んだのか?
BIツールやダッシュボードを提供しても、MRに活用されず、結局行動にはつながらない。
データを可視化しても、「何をどうすべきか」というサジェスチョンがない限り動きません。
DXS Stratify®は、判断に至るまでのプロセスが明確で、誰でも同じ結論にたどり着けます。
市場構造・競合状況・シェアなど、戦略因子が可視化された“共通地図”が共有されます。
これにより、現場と本社が同じ方向で動ける土台が整います。
DXの目的である「行動変容」と「成果創出」に直結する仕組みです。
デジタル投資が初めて“動く仕組み”として根づいたと実感しています。
だから私たちは、DXS Stratify®を導入します。分析で終わらないDXを実現するために。
【経営者・事業責任者の立場】
なぜ、私はDXS Stratify®を選んだのか?
個人の能力を高めるだけでは、もはや勝てない。いま必要なのは、組織力の最大化です。
「どこで勝ち、どこを捨てるか」——経営の本質は“選択と集中”にあります。
しかし、現場は各部門が別の地図を見ており、判断が属人的になっていました。
DXS Stratify®は、戦略の3因子(市場・シェア・競合)を一つのマップで統一します。
誰もが同じ根拠で語れ、意思決定の一貫性が全社に広がります。
営業、マーケ、教育、DX、それぞれが同じ方向を向き、連携できるようになりました。
結果として、“勝てる構造”が組織に内在化されてきています。
だから私は、DXS Stratify®を導入しました。全社を「勝ちに向かわせる組織」に変えるために。
■「考えて動け」と言うけれど…
👤 MRはこう言います:
「訪問先は多すぎて、どこに注力すればいいかわからない」
「勘や経験で回っているけれど、成果にはつながりにくい」
👤 営業所長はこう言います:
「チームの数字は見えても、なぜこうなっているのかがわからない」
「判断の根拠がないまま、人と時間を振り分けている」
👤 マーケティングはこう言います:
「データはある。でも、競合との関係性が見えず、戦略にならない」
「現場と同じ地図を見ていないから、響かない」
👤 研修担当はこう言います:
「戦略的思考を育てたい。でも現場は“実務とつながらない”と感じている」
👤 デジタル部門はこう言います:
「ツールは整っている。でも“動ける仕組み”になっていない」
「結局、誰も行動を変えていない」
これが、現場のリアルでした。
■ 全員が、“違う地図”を見ていた
問題は、能力ややる気の差ではありません。
各部門が、それぞれ別の視点で物事を見ている。
同じデータを見ていても、共通言語がなかった。
だから連携も生まれず、判断が属人的になっていた。
■ DXS Stratify®が“戦略の共通言語”になった
このジレンマを乗り越える鍵が、DXS Stratify®でした。
このツールは、
✅ 市場サイズ × シェア × 競合優劣 という戦略の3因子を
✅ 誰でも理解できる形で“地図化”し
✅ 部門を超えて「どこで勝つか」が語れる状態を作ります。
つまり、MR・所長・マーケ・教育・DX部門
すべてが同じ“戦略地図”の上で会話できるようになる。
結果として、
• 現場の動きに戦略性が宿り
• 本社の支援が現場に届き
• 教育が現場成果に結びつき
• デジタル投資が成果につながる
この状態こそ、戦略的組織が持つべき理想の姿です。
■ 経営に必要なのは、「管理ツール」ではなく「勝てる構造」
今、多くの企業が「管理の精緻化」に注力しています。
でも私は、それだけでは不十分だと思います。
必要なのは、“勝てる構造”そのものを社内に組み込むこと。
DXS Stratify®は、そのための戦略インフラです。
経営とは、“どこで勝ち、どこを捨てるか”の決断です。
その意思決定の根拠が、再現可能なかたちで整っている。
だからこそ、私はこのツールを選びました。
まとめ
DXS Stratify®は単なる「分析ツール」ではありません。
立場を問わず、「なぜ動くのか/どこに集中すべきか」を導き出す“戦略の方程式”です。
• MRには「自信を持てる行動指針」を
• 所長には「納得して動かせるマネジメント力」を
• マーケには「打ち手の正当性と連携の地図」を
• 経営には「投資判断の精度とスピード」を
• 教育部門には「戦略的思考の土台」を
• DX部門には「成果につながるDXの実装」を
それぞれに“使う理由”がある。それがDXS Stratify®の本質です。