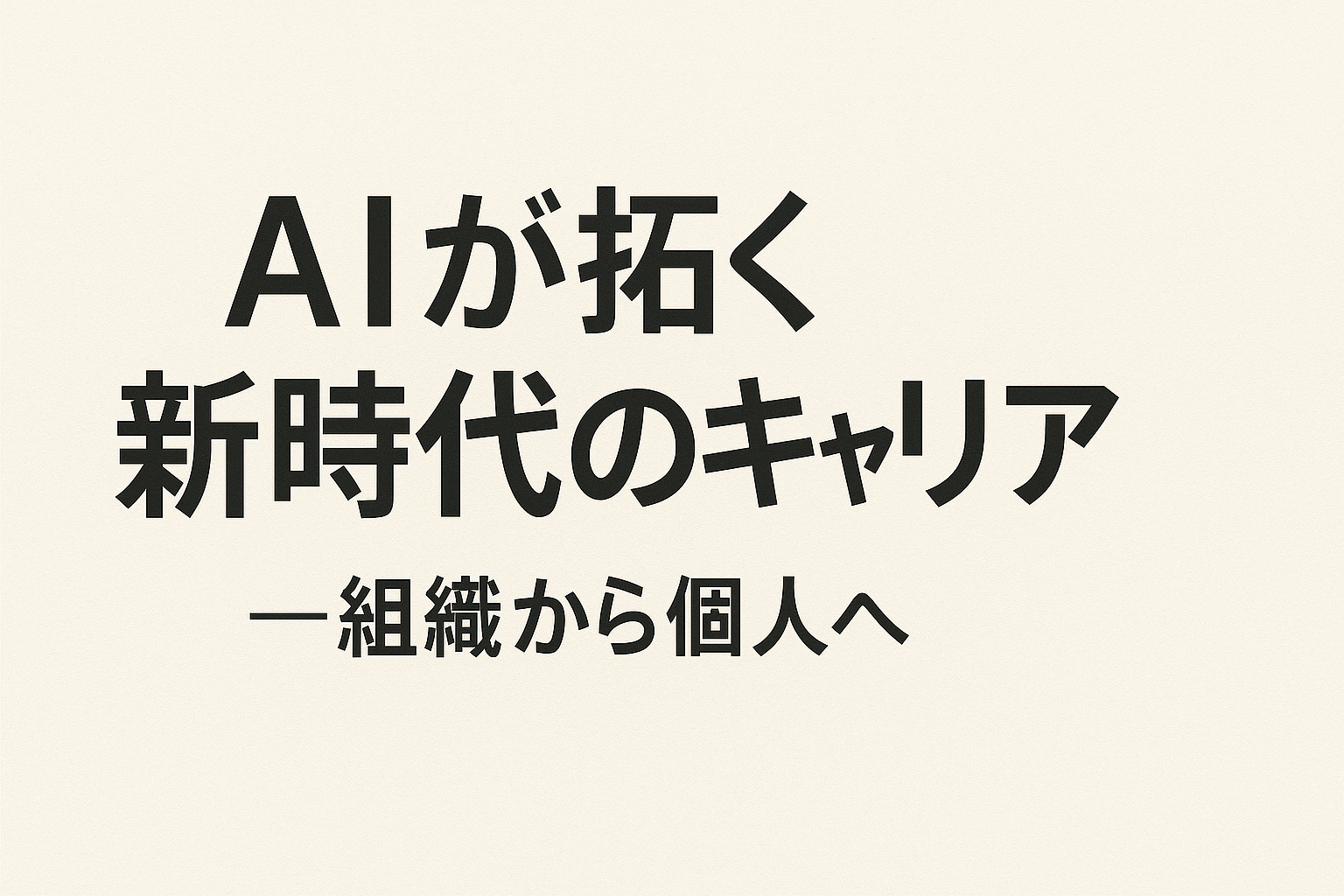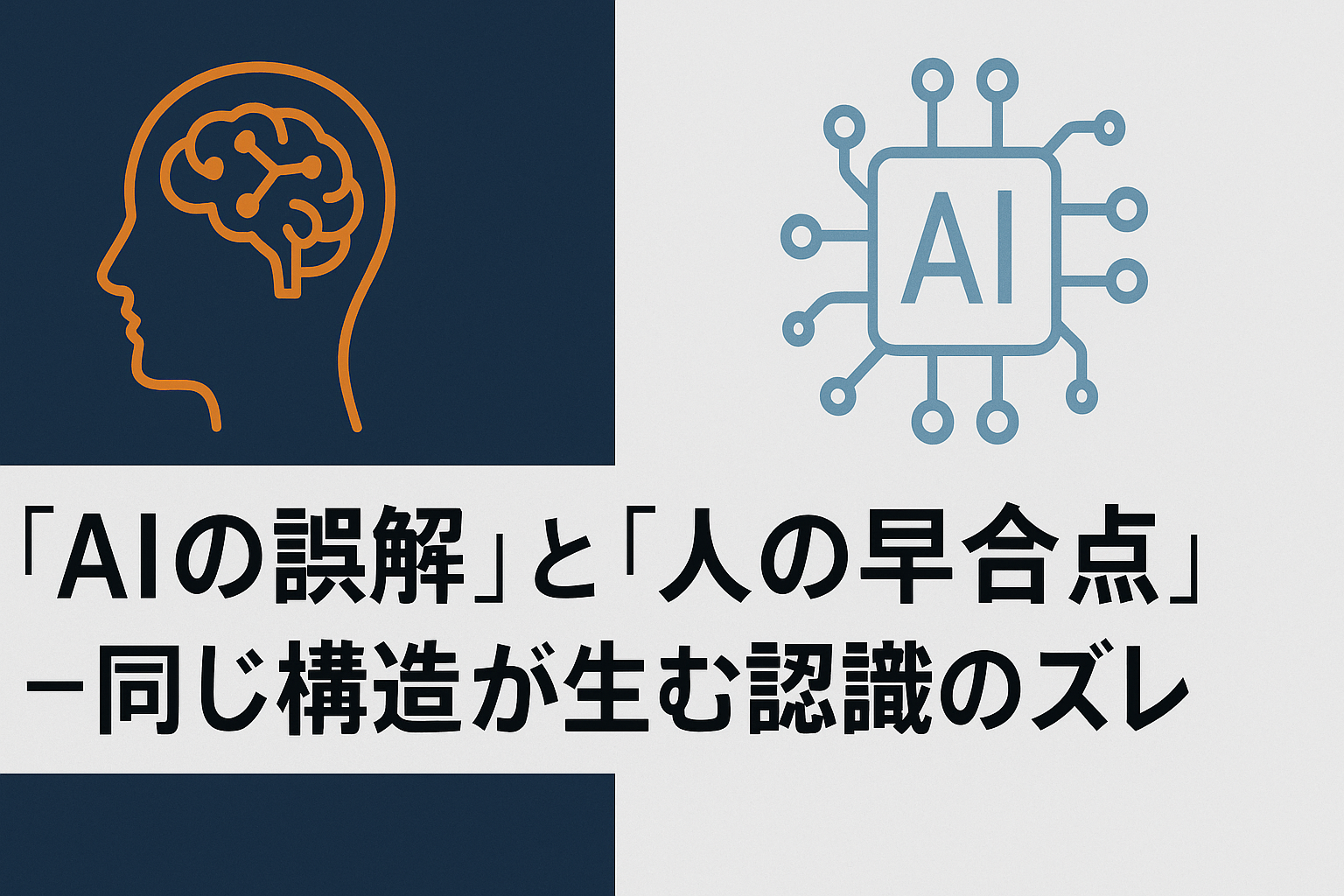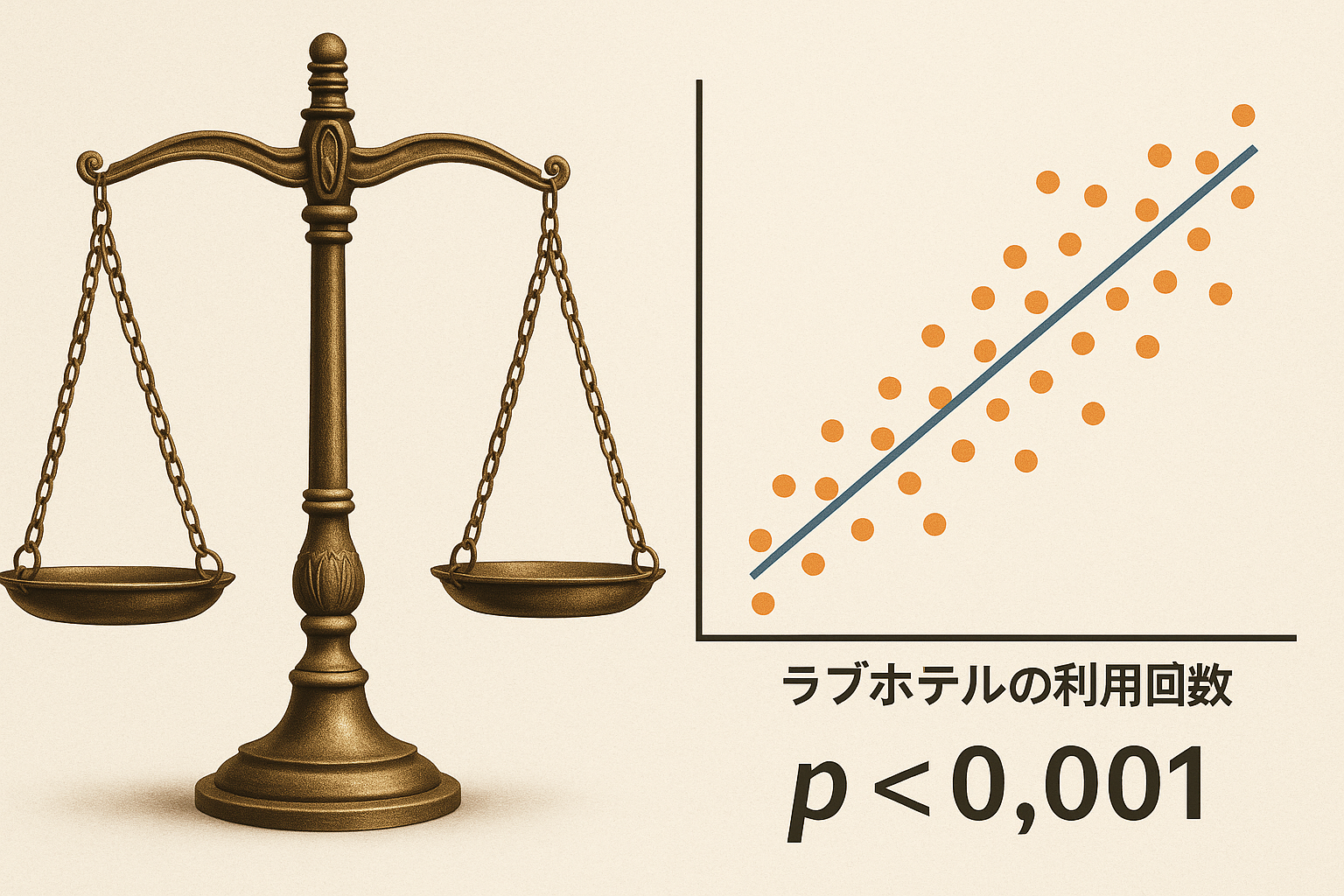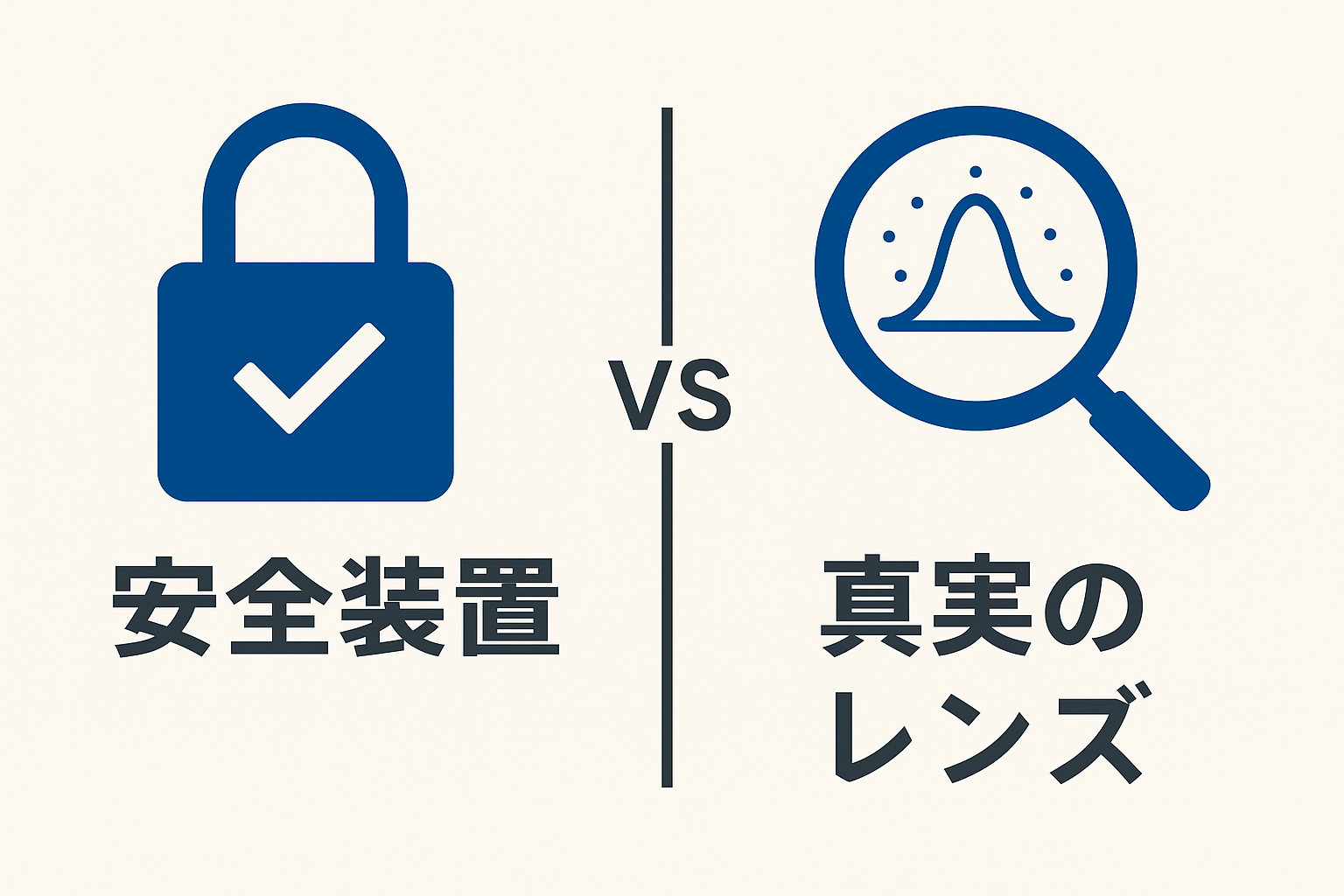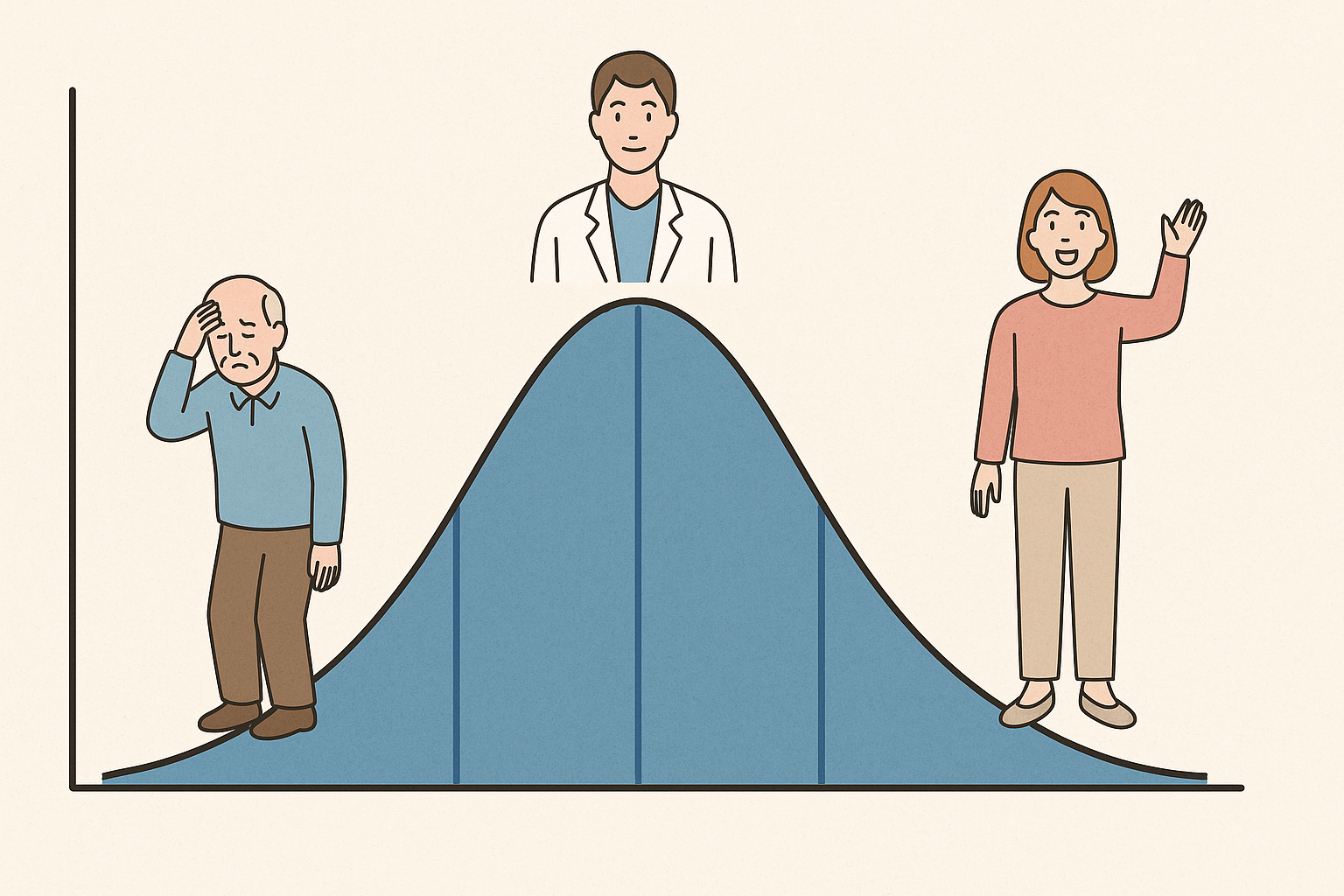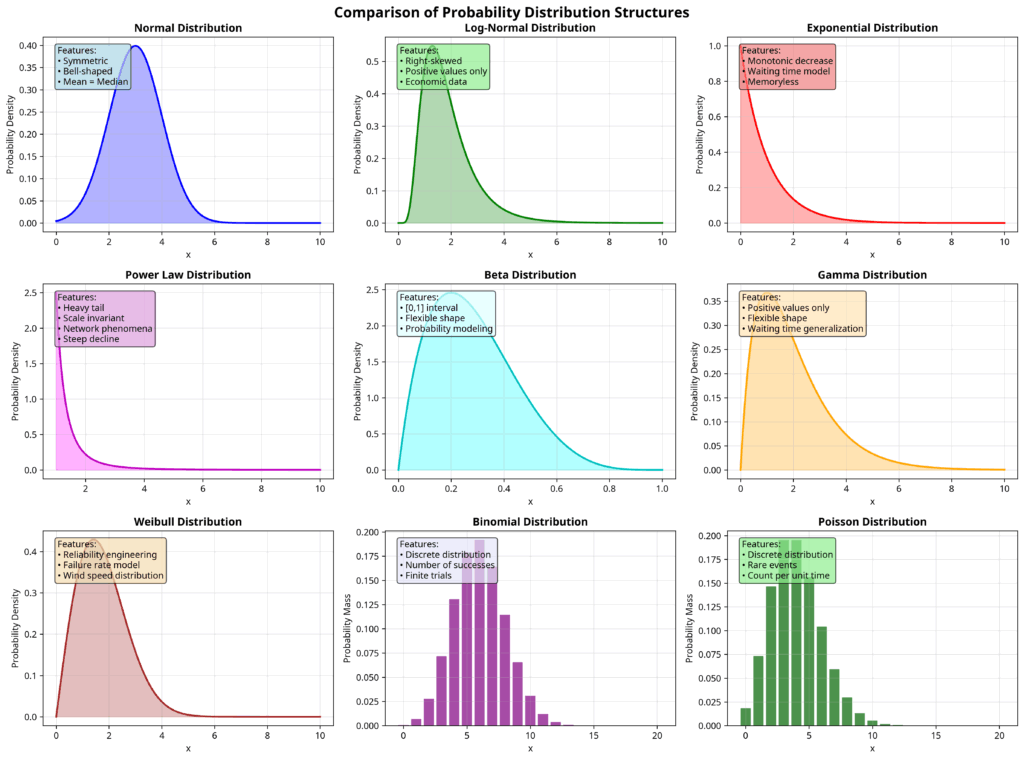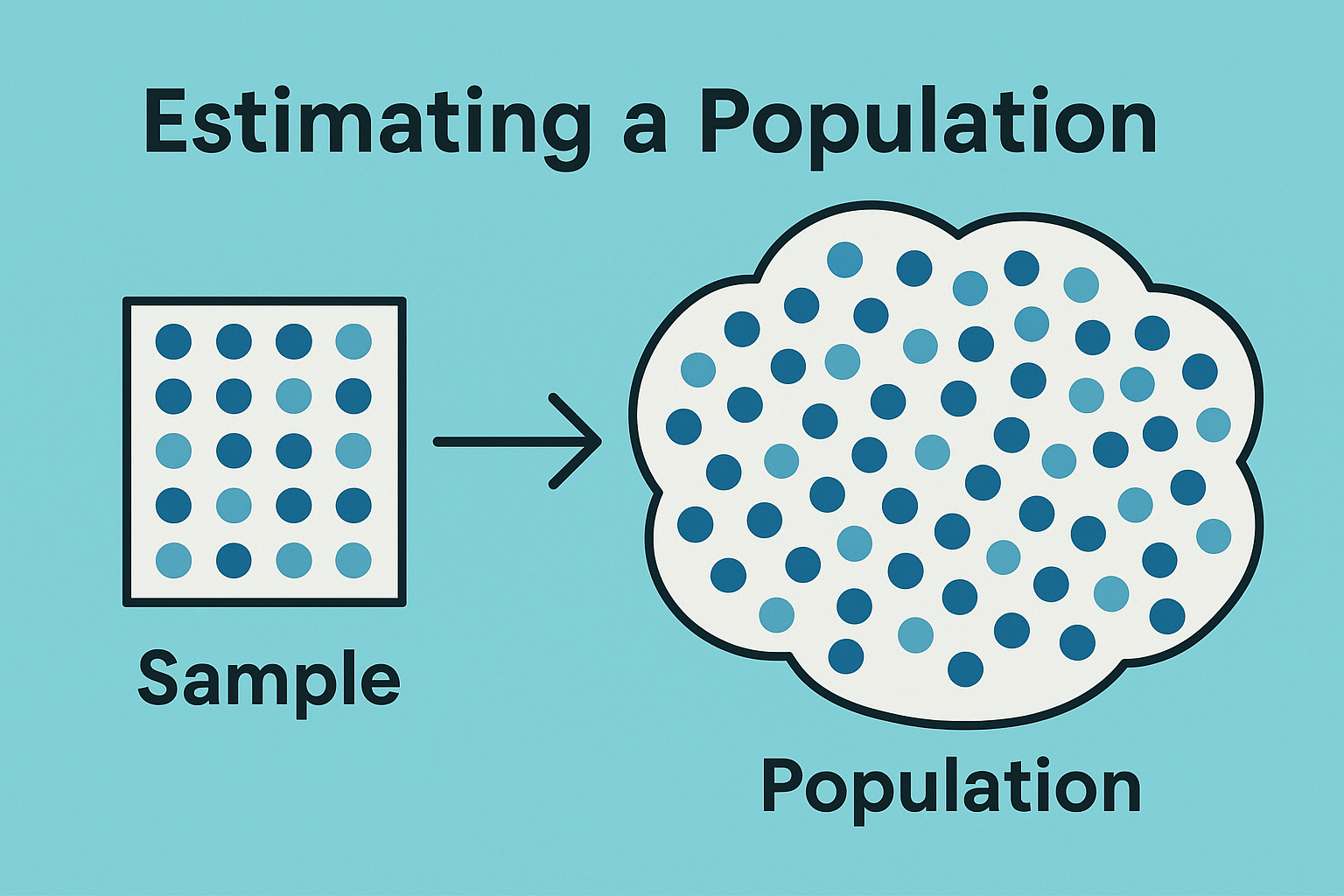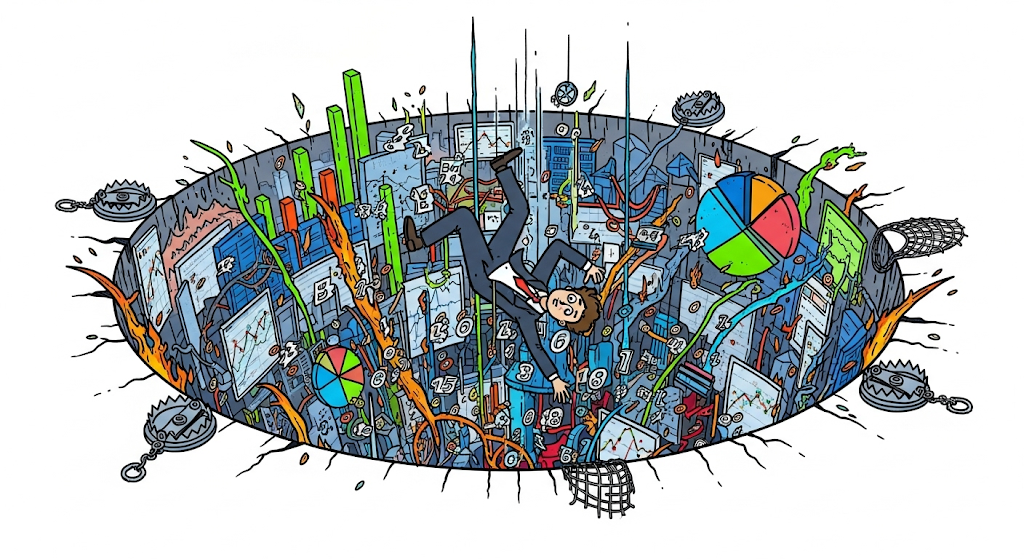今でもAIに対して懐疑的な声は少なくありません。
「ブラックボックスだから危険だ」「説明できない技術は信用できない」という議論は、その典型でしょう。
しかし私は、AIの本当の革新性はむしろそのブラックボックスにあると考えています。
私たちはスマートフォンで通話やナビゲーションを利用しながら、なぜそれが動作するのかを理解していません。
鉄の塊がなぜ海に浮かび、空を飛ぶのかを物理学的に説明できなくても、人々は船や飛行機を当たり前に利用しています。
技術の普及を決めるのは「理解」ではなく「体験価値」です。AIも同じであり、
「どう動いているのか」ではなく「何を可能にしてくれるのか」が本質です。
プロンプトエンジニアという新しい役割
AIを効果的に使うために必要なのは、すべての仕組みを理解することではありません。
大切なのは「正しい指示」を与えることです。
この役割を担うのが、いま注目されている プロンプトエンジニア です。
人間が 目的 と 守るべき条件 を提示し、AIがそのプロセスを担い、成果を返す。
発注者としての人間がゴールを定義すれば、プロセスの内部をすべて理解していなくても良い。
これは、外注や業務委託と同じ構造であり、「仕様を正しく伝えること」こそが人間の責任であり、AI活用の真価を引き出すことになります。
AIが広げる「個人の力」
これまで、知識や情報、専門性は組織に集約されていました。
個人がそれを活かすには、企業に勤め、役割を担い、組織の一部として働くしかなかった。
しかしAIは、かつて組織だけが持っていたリサーチ力や分析力、文章作成力を個人の手元にまで降ろしました。
いまや一人で調査会社を、戦略コンサルを、研究室を、そして編集部を持つことすら可能になったのです。
この変化は、組織に依存した従来のキャリアモデルを大きく揺るがす事実です。
組織は意思決定が遅く、既得権益を守り、責任を分散する構造を持っています。
その結果、むしろイノベーションを阻害する場面が少なくありません。
一方、AIを武器とした個人は、スピードと柔軟性を持ち、リスクを取って小さな実験を積み重ねることができます。
そしてその実験こそが新しい価値を生み出し、キャリアの資産となっていきます。
「課金が増える」ことは未来への投資
AIの普及が遅い言われる一方で、私は月を追うごとに課金額が増えています。なぜならそれは、AIが日常業務や思考の中で欠かせない存在になりつつある証拠だからです。
AIに投資するということは、自分の可能性を広げることに直結しています。かつてPCやスマートフォンに投資した人が、その後のデジタル時代をリードしたように、AIへの課金もまた未来を先取りする行為だと考えています。
結論
AIの革新は、組織に依存したキャリアを根本から変えつつあります。
- プロセスを理解しなくても、正しい指示さえ与えれば成果を得られる。
- 組織ではなく、個人が主役となって知を創り、発信し、信用を積み重ねられる。
- AIへの投資は、未来のキャリアを形作る「自己資本投資」そのもの。
これからのキャリアは、所属ではなく発信で信用を築き、AIを駆使して問いを立て、成果を生み出すことが可能です。AIは「自動運転システム」のようなものです。
AIが広げるのは、組織の力ではなく、個人の力の未来です。