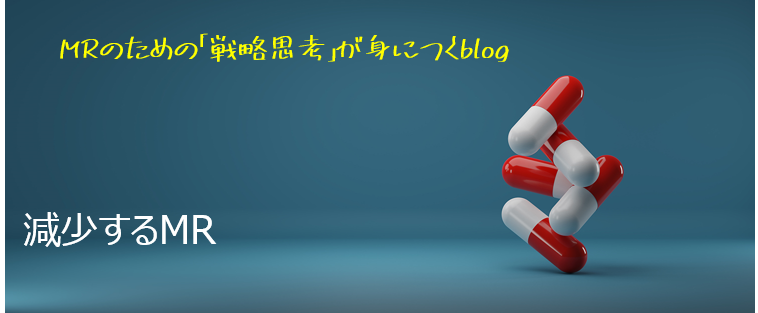処方獲得のために最も重要な顧客情報はなんでしょうか?
趣味や家族構成、休日の過ごし方などの嗜好性は治療方針や処方傾向を知る手掛かりになるでしょうか?
治療方針や処方傾向は、顧客である医師の年齢、地域、性別、職業、家族構成、年収などの影響を受けるでしょうか?
例えば家庭用消費材であるシャンプーの顧客ニーズを考えてみましょう。
用途や年齢など幅広い顧客が対象となるシャンプーですが、その種類には人気サロンなどで販売されている高級シャンプーから大衆向けの製品、アトピーの方向けの製品、育毛・発毛効果を謳った製品、保湿効果でしっとりする製品や指通り良くさらさらさせる製品、予めリンスが配合された利便性の高い製品など多岐に渡ります。
全ての顧客ニーズに応えることは出来ないため、シャンプーとしての基本的な用途はそのままに、市場全体ではなく、特定の顧客に経営資源を集中して製品を提供することで顧客の獲得および維持をするためです。
そのため顧客の嗜好性など非常に多くに情報を収集し分析する必要があります。
なぜなら対象は顔の見えない顕在化していない不特定の顧客だからです。
医薬品ビジネスの場合はどうでしょうか?
ターゲットは顔の見えない不特定の顧客でしょうか?
多くの製薬企業はターゲティングとコールアロケーションなどリソース配分まで明確に決めているはずです。
顧客の個人的な嗜好性は医療というフィールドにおいてはあまり大きな要因ではないでしょう。
顧客獲得だけではなく、顧客攻略が重要となるターゲットマーケティングでは顧客の行動変容を促す必要があります。
訪問、ディテール回数/内容、Web面談、ホームページへのアクセスなどの活動履歴が、顧客の処方に向かう行動変容をいかに促したか評価しなければなりません。
過剰な情報は時として判断や意思決定を困難にすることがあります。
本来重要ではなく必要性の低い情報を収集し記録することを負担に感じることは当然のことです。
マイナスのネジを回すにはマイナスドライバーがあれば十分です。






は処方インパクトが高いのか?③.png)
は処方インパクトが高いのか?②.png)
は処方インパクトが高いのか?①.png)