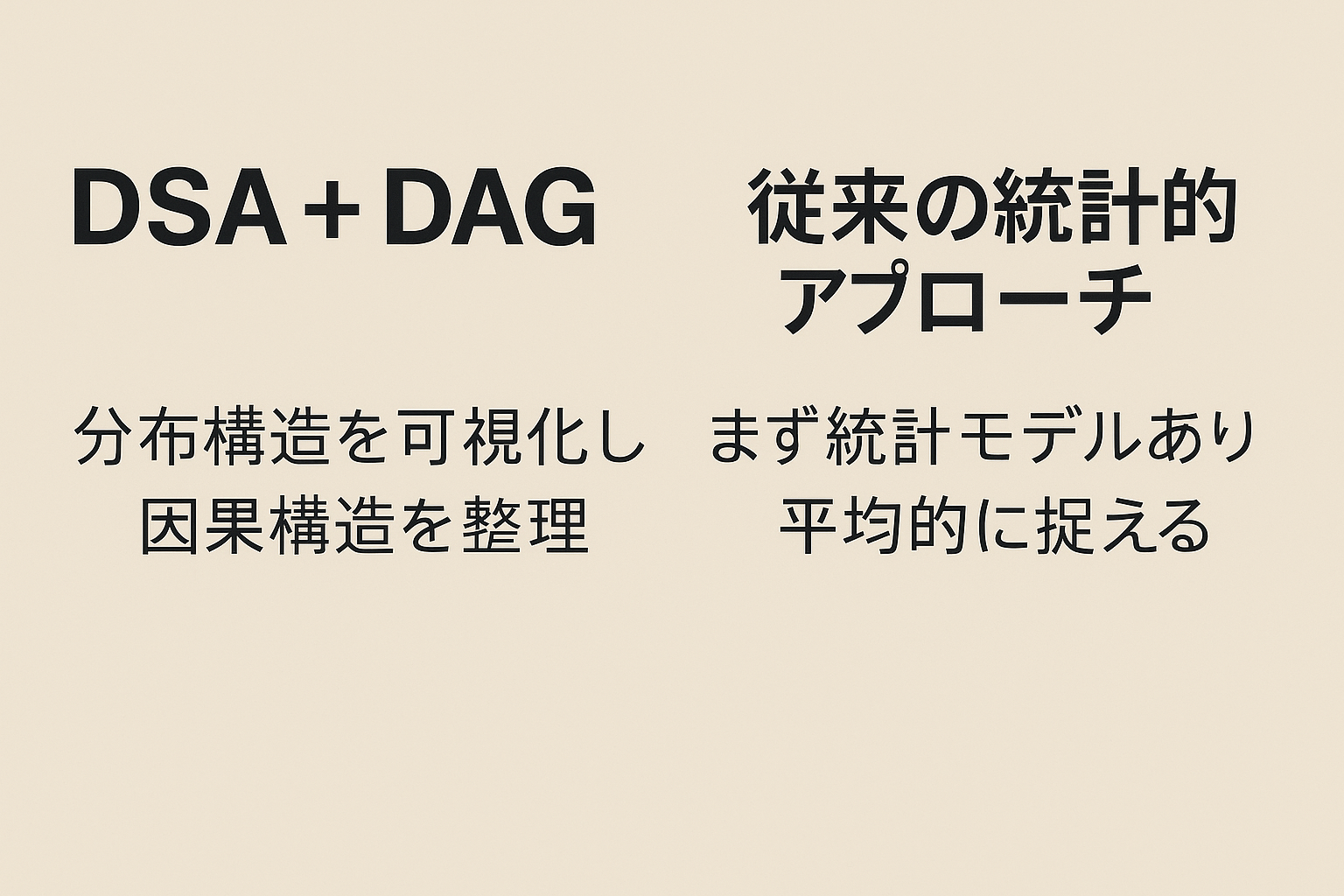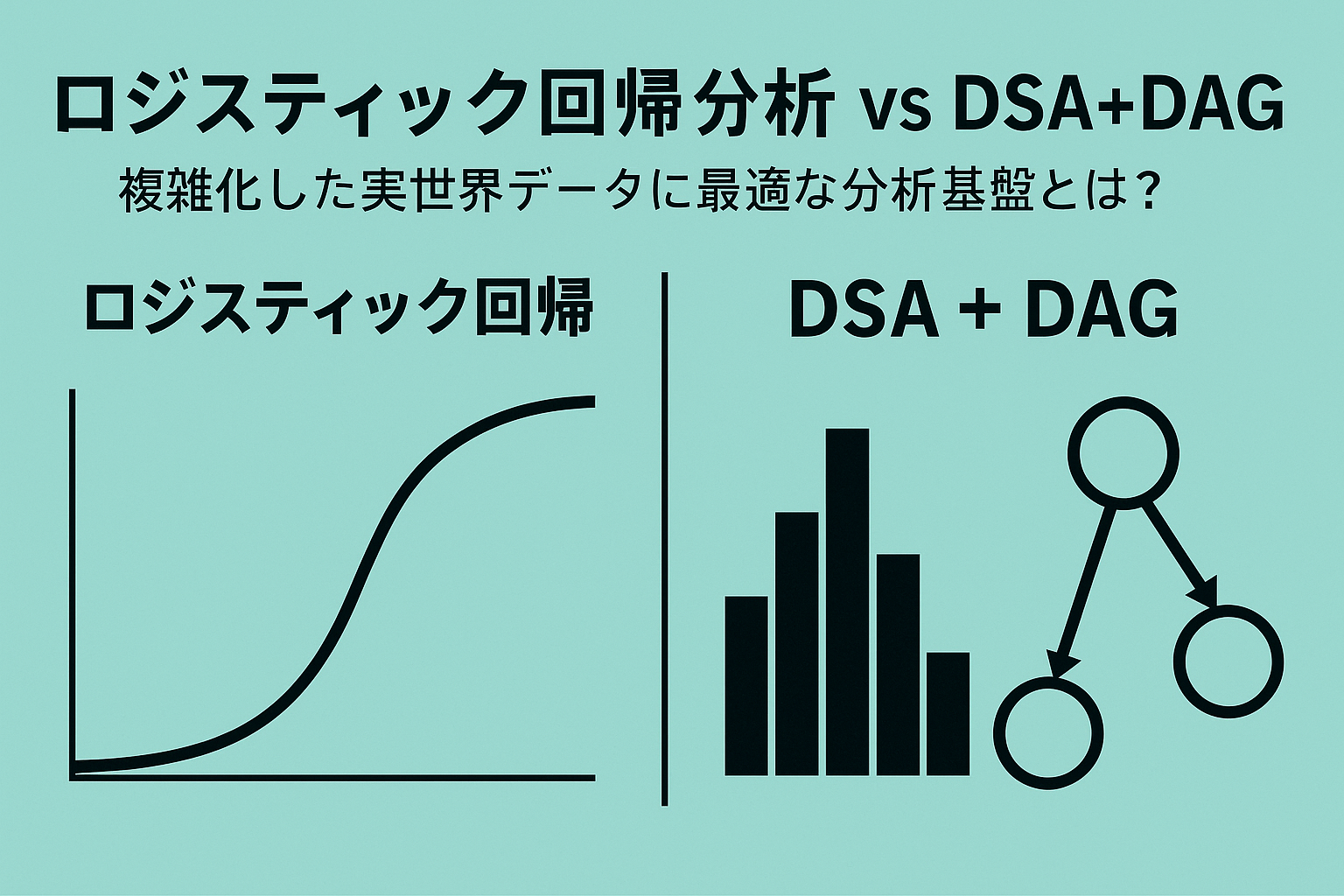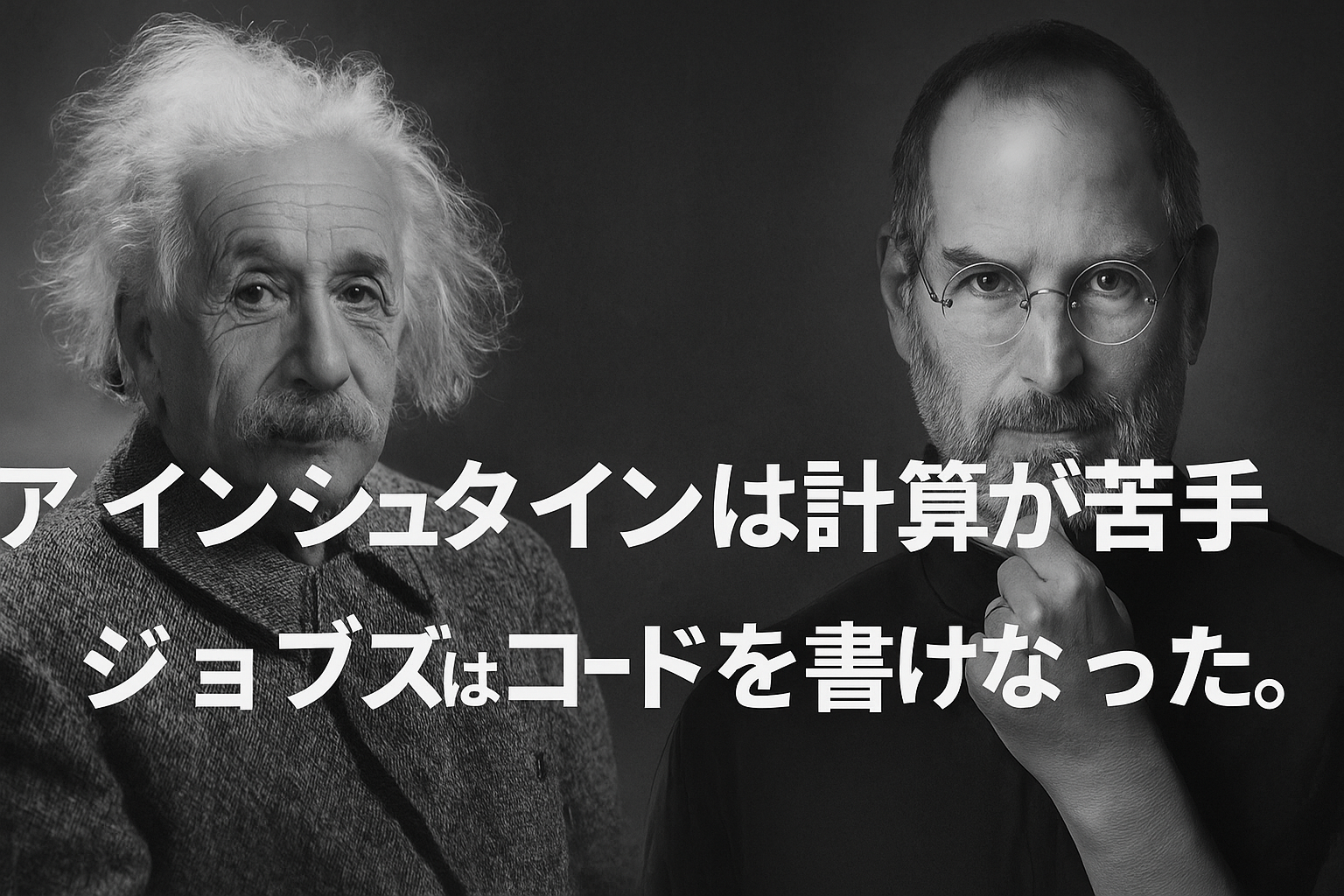――答えを聞かずに、意思決定の構造を読む技術――
営業や事業開発の場面で、つい聞きたくなる質問があります。
- なぜ検討が止まっているのですか?
- どんなリスクを感じているのですか?
- 誰の合意が必要なのですか?
いずれも一見、核心を突いた「正しい質問」に見えます。
しかし、こうした質問をそのまま投げた瞬間に商談が停滞する――そんな経験はないでしょうか。
正論の質問ほど、人は防御する
これらの質問に共通するのは、
すべて 「判断の責任」や「意思決定の正当性」 に触れている点です。
多くのビジネス現場では、
- 検討が止まっている理由
- 感じている本当のリスク
- 合意形成の力学
は、個人の怠慢ではなく、組織を守るための結果として存在しています。
そのためダイレクトに聞かれると、相手は無意識に
「説明できる答え」「安全な答え」
へと話を変えてしまいます。
結果として、本音や構造には辿り着けません。
ティプス①
「なぜ検討が止まっているのか?」を聞かない
その代わりに、こう聞きます。
- 「これまでに、似た話が出たことはありますか?」
- 「そのときは、どこまで進んだのでしょうか?」
ポイントは 過去形 です。
人は「今の判断」を説明するのは苦手ですが、
「過去の出来事」を語るのは得意です。
そこから、
- 過去の失敗体験
- 忙しさによる中断
- 判断できなかった組織構造
が自然に見えてきます。
“止まっている理由”は、現在ではなく過去にあります。
ティプス②
「どんなリスクを感じていますか?」を聞かない
代わりに、こう聞きます。
- 「もし進めるとしたら、一番気を遣うのはどこでしょう?」
- 「逆に、ここだけは変えたくない、という点はありますか?」
この質問で出てくる言葉こそが、
相手が本当に警戒しているリスクです。
多くのケースで、リスクの正体は
- 技術的失敗
- 数値的損失
よりも、
- 説明責任
- 社内調整
- 手間が増えること
にあります。
人は「損」よりも「面倒」や「責任」を恐れます。
ティプス③
「誰の合意が必要ですか?」を聞かない
代わりに、こう聞きます。
- 「こういった話は、普段どこで共有されることが多いですか?」
- 「進めるとしたら、最初に相談すると安心なのは誰でしょうか?」
ここで重要なのは、
決裁者の名前を知ることではありません。
本当に知るべきなのは、
- 暗黙の拒否権を持つ人
- 前例を握っている人
- “一言で空気を変えられる人”
です。
組織は、公式ルートより非公式の力学で動いています。
営業で見るべきは「答え」ではない
質問の目的は、
YES/NOを引き出すことではありません。
- 話すスピード
- 言葉の濁り
- 主語の変化(私 → 部署 → 会社)
- 無意識の言い換え
こうした反応の変化こそが、
その組織が動かない理由を教えてくれます。
まとめ
ビジネス・営業で失敗しない質問の原則
- 正しい質問ほど、直接は聞かない
- 本音は「過去」と「仮定」の話に出る
- 組織は個人ではなく、構造で止まっている
だから、答えを求めない。
でも、必ず分かるように聞く。
この問い方ができると、
営業は「説得」ではなく、
意思決定の構造を読み解く仕事に変わります。